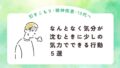千葉県にある元ひきこもりスタッフだけで運営する「カフェ コッソリ」で働く、なびさんにインタビューしました。
ラテアーティストで、テレビ取材も受けたこともあるなびさん。
そんな彼に、ひきこもりだった過去から現在に至るまでの経緯、そしてひきこもりの方へのメッセージまで、じっくりお聞きしました。
――ひきこもるようになった背景や、きっかけがあれば、話していただけますか?
もともと、小学校高学年くらいのときに、友達とちょっとしたトラブルがあって。そこから人が怖くなりました。
小学校、中学校、高校はなんとか行けていたんですが、友達はいなくて。
19歳、大学生になったときに、電車に乗れなくなったんです。
周りの人に悪口を言われているような気がして、次の駅に着くまで苦しくなったりしてしまって。
大学に行けなくなってしまいました。
そして、精神科に行くと「精神分裂病(今の統合失調症)」と診断されました。
そうなった背景には「大学に入って自分と周りの差を感じたこと」があると思います。
みんなやりたいことに向かって頑張っていたり、サークルで楽しそうに充実しているのを見て、それに対して自分はやりたいこともないし…と。
「キラキラした周り」と「何もない自分」を感じてしまっていました。
――ひきこもりの頃はどんな生活をしていましたか?
精神科に1週間に2回、デイケアと診察のために両親と行く以外は、家でずっと過ごしていました。
眠剤を飲んでも眠れなくて、明け方に寝て、夕方に起きて…と、昼夜逆転した生活でした。
家ではずっと横になってテレビを見たりしていました。
1年で110キロくらいまで体重が増えました(笑)
――ひきこもりだった頃、自分の将来についてどんな風に考えていましたか?
25年以上前のことなので、精神疾患の人は周りに居なくて、テレビでは精神疾患の人が事件を起こしましたみたいなニュースが流れていて。
親も僕も精神疾患のことは周りに隠していました。
その頃は外に出ることはできないから、働くことは考えられないし、将来良くなるかもわからない。
でも心のどこかで、いつか、何年かしたら、働けるようになって、青春っぽいことをして、恋人ができて家族ができて…みたいなことを考えていました。そんな妄想をすることで、何もかもうまくいかない今の自分から逃げて(笑)
全くもう未来が終わったという感じではなく「妄想しているものにいつかなれたらいいな、今は何もできないけど」という感じでした。
――今のお仕事の内容を簡単にでいいのでご説明していただけますか?
主にドリンクを作っていて、調理をちょこちょこ手伝ったりもしています。
あとは…ラテアート。ラテアートが好きでずっとやってて、今もお客さんに提供しています。
それと接客。さちさん(もう一人のスタッフ)がいないときはホールをやっていますし、いるときも「ちょっと行かせて」って言ってやったりしてます(笑)
――ひきこもりだった状態から今のお仕事をするまでの経緯を教えてください。
19歳で精神疾患を発症して、2年間ひきこもって。
21歳で大学、違うところに入り直して、25歳で卒業して。
一旦会社に入るんですけど、すぐに辞めちゃって。
で、25から30になるまでは、いろんなアルバイトとかを応募をして、受けに行って。受かったところも、1日で逃げちゃったりとか…だいたい続かなくて。
あとは倉庫の短期バイトを繰り返すような感じで。
で、30になって、焦り始めて。
主治医に相談したら就労移行に通うことになって。
一年後に特例子会社っていういろんな障害の方が集まる会社に就職して。そこで障害者雇用で5年間正社員で働くんですけど。結局またメンタル崩しちゃって、辞めて。
で、ララホーム(カフェコッソリと関わりの深い福祉事業所)に通いだして。
ララホーム3年目くらい…30代後半のときから喫茶店でパートで働きだして。
で、途中からラテアートの活動を個人で初めて。
それで、ラテアート一本でいろんなカフェに行ったりする活動をするようになってから、声がかかって、去年ここで働くことになった…という感じです。
――苦手な事(たとえば対人恐怖など)とどのように向き合い、克服していきましたか?
相手が自分に怒っているんじゃないか、嫌っているんじゃないかという不安が強かったので、そういう場面では相手の気持ちを確かめる、ということをしていました。「僕のこと怒ってます?」って。聞きに行くのはすごく怖いですけど。
相手を「自分を嫌っている人」かもしれないと思ってしまうと、その人の仕草や言葉がすべて「自分のことが嫌いなんだ」と思う材料になってしまったり、避けてしまったりして。
そういうことが起こらないように、挨拶を先にしに行くとか、返事だけ元気にするとか、そういうのをやっていました。
ラテアートも、対人恐怖を克服するきっかけになりました。
本当にラテアートは楽しくて、好きで。
ただ作るだけじゃなくて、お客さんに提供したい。ちょっとお話できたらいいな。できたらちょっと喜んでほしいな…という気持ちが強くあって。
それで、人は怖いけど、話してみようと。
人が怖いからって避けていたら、ようやく見つけたやりがいとか喜びが薄れていってしまうかもしれない…と。
そのときはそこまで考えていなくて、勢いで「話したい!」という感じでしたけど。
あとは、失敗することも怖くて。
ミスしたらどうしようって不安になるとか、怒られたとか、そういうことがきっかけで20代の頃はすぐに仕事を辞めてしまったりとかしていました。
でも、ちょっと粘って、「怖いもう行かない」って思っても行ってみる。もちろん無理のない範囲でですけど。
僕なりの解決方法を話してきましたけど、対人恐怖とかってやっぱりすぐにはよくならなくて。
今言ったことをやって、ちょっとずつ良くなって、どっかで何かあるとまた戻っちゃう。
登っていたのが一旦くだっちゃうんですけど、そこでやめずに、一旦休みながらまたちょっとずつ続けていく、っていうのを数年やってたら、だいぶそれで良くなりました。
「一発で良くなること」を欲していたんですけど、そういうことはないから、それでも根気強く付き合っていったら、少しずつ良くなったかなと思います。
――今までの人生で、一番「してよかった」と思う行動はなんですか?
ラテアート…ですかね。
いっぱいありすぎて迷いますけど(笑)
ラテアートを始めたことが一番大きいです。
ラテアートとはじめて出会ったのは、ひきこもっていたときで。
両親が朝、喫茶店に行こうって誘ってくれて、モーニングセットのラテにたまたまラテアートが描いてあって。それがすごい嬉しかったんです。
で、自分もやりたいなと思ったんですけど、ラテアートをするには、カフェとかで働く必要があるじゃないですか。
でも人怖いし仕事すぐ辞めちゃうし、接客とか自分には絶対無理!と思ってたんで。
それが20歳のときで、ラテアートを始めたのは38歳くらいのときで。
もうラテアートのことは忘れかけていたくらいだったんですけど(笑)やりたい、という想いはやっぱりあって。
ラテアートをきっかけに、過去の職場の人や、小学校時代の同級生が来てくれたりとかして。
自分が絶対嫌われていたと思っていた、自分の暗黒時代の人たちなので、自分から会うのはやめてたんですけど。
そういう方たちが来てくれて「あ、意外と自分の過去とかそんなに悪くなかったんだな」って思えて。
あとは、ラテアートの活動でいろんなカフェを回って、そこの店長さんとかお客さんとか、そういう人との繋がりを持てたのも大きかったです。
――今までの人生で、特に支えになったものはなんですか?
両親だったり、ちっちゃい頃からの楽しかった思い出、あとは人との繋がりかなと思います。
――過去の自分に声をかけるとしたら、どんな言葉をかけたいですか?
過去の自分にアドバイスというか、お説教をするイメージなんですけど(笑)
ちゃんとその、喜怒哀楽。「嬉しい」とか「楽しい」とか、逆に「むかつく」とか「悲しい」とか、感情を自分に蓋をせずに、ちゃんとまずは感じて。
で、それを相手に嬉しかったら嬉しいと伝えてく。なんかちょっとむかついたら、ちゃんと伝えるとか。
仲直りしたかったら「ごめん」って言うとか。
それを全部やってこなかったんで。
それを「ちゃんとやろうねー」と伝えたいです。
で、それを聞いてくれたり受け止めてくれる人がいたら、ちゃんとその人を大事にしようね、ということをアドバイスしたいと思います。
――同じようにひきこもりで悩んでいる人に伝えたいことはありますか?
ひとりで抱え込まないようにしてくれたらいいなあと思います。
自分のことを想ってくれている、見てくれている人はいるよということも伝えたいです。
そんな人いないと思うかもしれないし、実際自分もそうでした。
でも、もしかしたら気付いていないだけで、もうすでに周りにいるかもしれません。
あとは、夢中になれる好きなものをなにかひとつでも見つけてほしいなと思います。
「見つけなければ」と焦る必要はないですけど。
続かなくてもいいので、とりあえずいろいろやってみたり。
なんでもいいし、仕事にならなくてもいい。
一番伝えたいのは、うまくいかなかった経験は、無駄にならないということです。
友達ができなかったこと、対人恐怖を抱えていたこと、ひきこもったこと、仕事をすぐ辞めたこと、そういう経験すべてが無駄じゃなかったと思っています。
この経験があるからこそわかることをお客さんなどに話すことができていますから。
友達がいない時期があったからこそ、周りの人に感謝できるようにもなりました。
当時は「こんな人生じゃなければ」と思っていましたけど、すべての経験が今に繋がっていると思っています。
そう思えるようになるまでには、僕みたいに2、30年かかるかもしれないし、もっと短いかもしれないし、もっと長いかもしれないけれど。
「うまくいかなかった経験が支えになるときが来るよ」って伝えたいです。